はじめに
皆さんこんにちは、ENです。
この記事は、前回からの続きです。
Money Forwardで支出の把握
育休による無収入期間に備えて、まず取り組んだのは、家計簿アプリで支出を把握することでした。
使ったアプリは、「Money Forward(無料版)」です。
クレジットカードや銀行口座と連携したのですが、当時はこの便利機能を使いこなせなかったため、レシート読み込み機能を使っていました。(現在はクレカを連携し、快適そのものの家計簿ライフを送っています。)
レシート読み込み機能は、スマホやタブレットのカメラでレシートを読み込むだけで、購入日、購入店舗、支払金額、費用項目を自動で入力してくれる便利な機能です。

購入店舗、費用項目はうまく読み込めないこともあったため一部手入力していましたが、それでも便利でした。
現金払いをしている方は、レシート読み込み機能を使うと便利だと思います。
一方、キャッシュレス決済を基本としている場合は、Money Forwardと使用しているクレジットカード等を連携させると自動で購入履歴を読み込んでくれるため、入力の手間がほぼ無くなります。
※連携を始めたばかりだと、仕分けがうまくいかない(食費が日用品費になっているなど)ことがありますが、後から自分で変更できます。
私は楽天カードを連携していますが、無料版だと1週間弱のタイムラグがあるものの、きちんと購入履歴が反映されています。
1ヵ月の支出が判明
本題に戻って・・・1ヵ月入力を継続すると、こんな感じで家計の支出がわかります。
※ENの場合、Money Forwardでは支出を把握したいため、収入は入力していません。
※当時のデータが残っていないため、2023年3月のデータを例示します。
「食費」の項目をタップすると、より細かい情報がわかります。(下の画像)
※一部購入店舗情報を消しています。
こうしてそれぞれの項目を確認するだけでも、「今月はコンビニ利用が多かったけど、どうしてだろう?」とか、「遠出したわけでもないのに娯楽費が高かったな」など、自分の支出の全体像が見え、財布の引き締めにつながります。
2~3ヶ月続けると、大体の支出傾向が分かってくるため、②以降の行動がスムーズに進むと思います。
Money Forwardは有料版もある
今回紹介したMoney Forwardですが、有料版もあります。
無料版との比較を表に示します。(支出を把握するために使用する機能に限定)
より詳細に知りたい方は、公式サイトで確認してください。下記にリンクを貼り付けます。
(https://moneyforward.com/pages/premium_features)
| 無料版 | 有料版(スタンダード) | |
| データの閲覧 | 過去1年分まで | 1年以上前のデータも閲覧できる |
| 連携できる金融機関数 | 4件 | 制限なし |
| 連携口座の更新頻度 | (ENの場合)1週間弱で反映 | 無料版より高頻度 |
| 連携口座の一括更新 | 不可 | 可(一部非対応の金融機関あり) |
| ※グループ作成 | 1件 | 制限なし |
※グループ作成 とは、連携した金融機関の口座や現金、資産のうち、一部に絞って表示をする機能です。
たとえば、「証券口座や定期預金等の資産グループ」と「日常使いの銀行、クレジットカードの履歴を反映するグループ」といった使い方ができるかと思います。
スタンダードプランは月額500円程度で、連携できる金融機関数が無制限になるなど、「収支管理も証券口座も副業の管理も何もかも済ませてしまいたい。」という方にとってはいいプランかもしれません。
また、家族(主に配偶者)のクレジットカードや銀行口座も連携させたい場合は、自ずと連携金融機関数は増えるでしょうから有料版も検討の余地があると思います。
ENは無料版を使い続ける理由
ただ、
・支出さえ管理できれば良い
・使うクレジットカードは1枚、銀行口座もせいぜい2つくらい
・1ヵ月単位で支出がわかればいいので、更新はさほど急がない
・去年のデータは不要
という私のようなタイプであれば無料版で十分だと思います。
私の場合、スタンダードプランの中身を使いこなせないと考えたため、無料版を使い続けています。
銀行口座もクレジットカードも、持ち物は少ないに限ります。
家賃支払いや子どもの学校徴収金等の兼ね合いでどうしても口座を増やさなければならない場合は、その口座は連携せず、ポチポチ手入力しようかなと思っています。
また、配偶者のカードや銀行口座は連携せず、「家計を把握したい」と理由を伝えた上で都度聞くようにしています。
連携させてほしいと言えば連携させてくれるとは思いますが、聞けば教えてくれるのでそれで良いかなと。
一応、聞きっぱなしではなく、配偶者には家計の状況を定期的に(3か月に1回くらい?)報告しています。
資産のポートフォリオや収入は、証券会社のマイページやExcel(スプレッドシートでも〇)で十分管理できると考えています。
それでは今日はこのあたりで失礼します。
次回は②③に進みます。

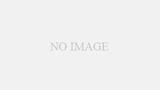
コメント